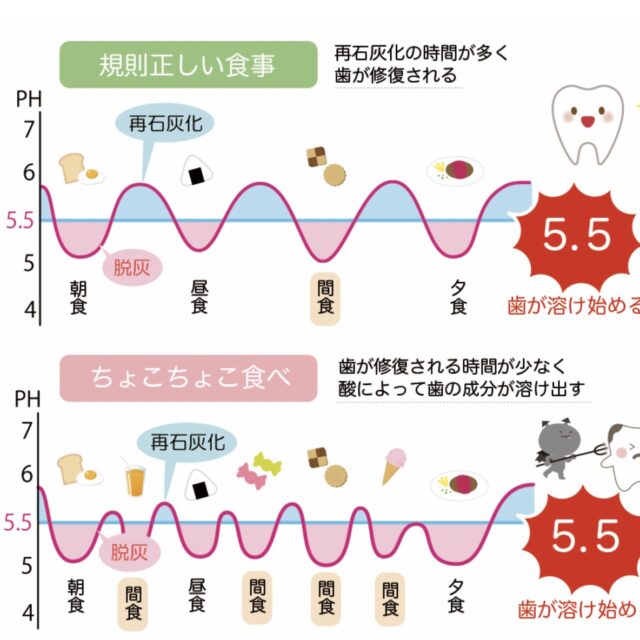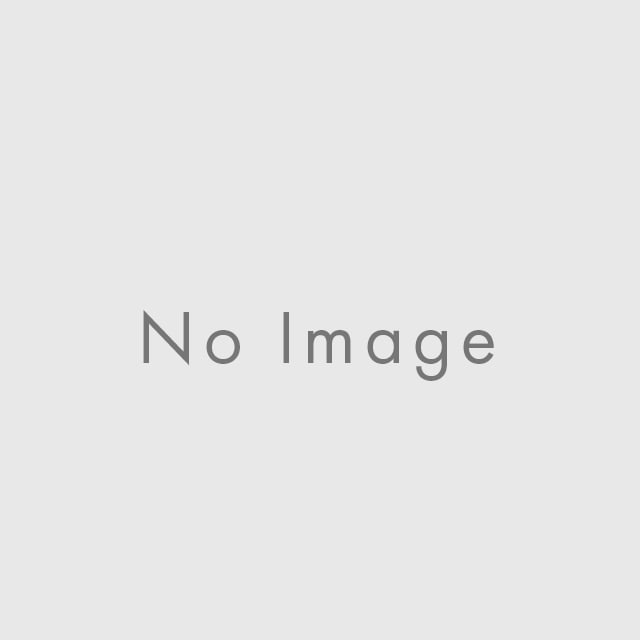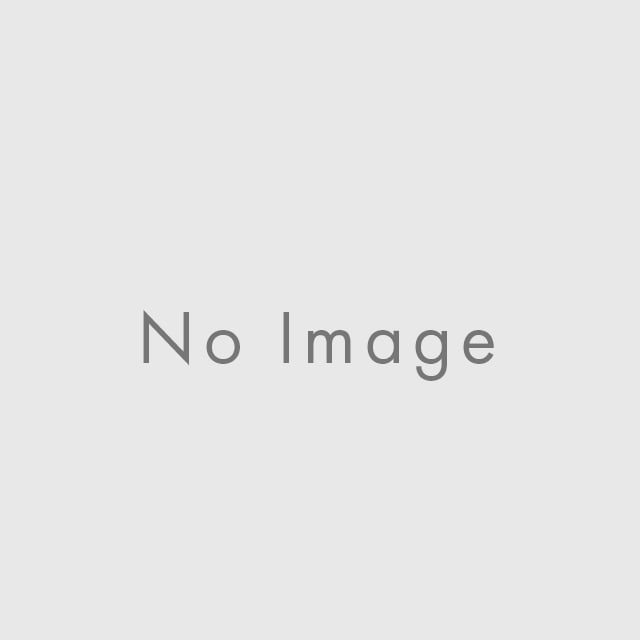目次
歯石取りの際の痛みが不安で、定期的なクリーニングをためらっている方へ
「歯石取りは痛い」というイメージをお持ちの方や、過去に経験した痛みがトラウマになっている方も少なくありません。特に、歯周病の進行具合によっては、歯石除去の際に不快な刺激や出血を伴うことがあります。しかし、歯石は歯周病の最大の原因の一つであり、そのまま放置すれば大切な歯を失うリスクが高まります。痛みへの不安から予防や治療を遠ざけてしまうのは、口元の健康にとって大変もったいないことです。
このページでは、歯石取り(スケーリング)がなぜ必要なのか、そして「痛み」や「出血」はどのような状況で起こり、どのように対処できるのかについて、詳しく解説いたします。私たちは、患者様の不安を和らげ、できる限り快適に処置を受けていただくための様々な配慮を行っております。歯石取りに対する正しい知識を持つことで、安心して定期的なケアを受けられるよう、ぜひ最後までお読みください。
歯石取りとは?
歯石取りとは、歯科医院で行う専門的なクリーニング処置の一つで、医学的にはスケーリングと呼ばれます。文字通り、歯の表面や、特に歯と歯ぐきの境目、そして歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)の奥にこびりついて固まった「歯石」を除去する処置です。
歯石が形成されるメカニズム
- プラーク(歯垢)の石灰化:歯磨きで取り残されたプラーク(細菌の塊)は、唾液に含まれるカルシウムやリン酸などのミネラル成分と結合し、時間の経過とともに硬く石のように変化します。これが歯石です。
- 形成部位:歯石は、主に唾液腺の出口に近い下あごの前歯の裏側や、上あごの奥歯の外側にできやすい傾向があります。
- 歯石の特徴:歯石は非常に硬いため、日々の歯磨きやフロスでは取り除くことができません。また、歯石の表面はザラザラしており、新たなプラークが付着しやすい「細菌の住処」となってしまいます。
歯石取りの重要性
歯石そのものは無菌ではありませんが、そのザラザラした表面に付着・増殖する細菌(プラーク)が、歯ぐきに炎症を引き起こし、最終的に歯を支える骨を溶かしていく歯周病の直接的な原因となります。
歯石を除去することで、プラークが付着しにくい清潔な状態を保ち、歯周病の進行を防ぐことができます。歯周病予防において、この歯石取りは非常に重要な基本治療の一つと位置づけられています。
歯石取りで痛みはある?
歯石取りの際に「痛みがあるかどうか」は、患者様のお口の状態や体質、そして歯石の付着状況によって大きく異なります。結論から申し上げると、多くの場合、我慢できないほどの強い痛みを感じることはありませんが、不快な刺激や軽い痛みを感じることはあります。
痛みを感じる主なケース
- 知覚過敏がある場合:歯ぐきが下がっていて、歯の根(象牙質)が露出している方は、超音波スケーラーの振動や水に触れることで、一時的に「キーン」としたしみるような痛み(知覚過敏)を感じやすい傾向があります。
- 歯周病が進行している場合:歯周ポケットが深く、歯ぐきの下(歯根面)にまで大量の歯石がこびりついている場合、深い部分の歯石を取り除く際に歯ぐき内部に刺激が及び、痛みを感じやすくなります。特に炎症が強い歯ぐきは敏感になっています。
- 歯石の付着量が多い場合:長期間、歯石取りを受けておらず、歯石が厚く、強固に付着している場合、それを剥がす際に、周囲の歯ぐきに圧力がかかり、痛みや圧迫感を感じることがあります。
痛みを軽減するための配慮
中目黒BIANCA歯科では、患者様の痛みの不安を軽減し、できる限り快適に処置を受けていただくため、以下のような配慮を行っています。
- 器具の選択と調整:超音波スケーラーの出力レベルを細かく調整し、患者様の痛みの程度に合わせて振動や水の量を加減します。また、手用の器具(ハンドスケーラー)と組み合わせて使用し、刺激の少ない方法を選択することで、痛みを最小限に抑えます。
- 丁寧な声かけと確認:処置中は患者様の状態を常に確認し、痛みや不快感がないかを都度お伺いします。これにより、患者様が我慢することなく、ペースに合わせて治療を進めることができます。
- 定期的なクリーニングの推奨:歯石が溜まりすぎると、除去の際に痛みを感じやすくなります。3ヶ月〜半年に一度など、定期的にクリーニングを行うことで、一度に除去する歯石の量を減らし、痛みのない快適な処置につなげることが可能です。
処置中に痛みを感じた際は、我慢せずにすぐに歯科医師や歯科衛生士にお伝えください。
歯石取りをした時に血だらけになってしまう理由
歯石取りの際に出血があると、「何か問題が起きたのではないか」と驚かれる方もいらっしゃいますが、これはお口の中が病的な状態にあることのサインであり、通常は処置が失敗したわけではありません。歯石取りで出血が見られる主な理由は、歯ぐきに炎症が起きているからです。
出血の主な原因は「歯ぐきの炎症(歯周病)」
- 歯石に付着した細菌の刺激:歯石のザラザラした表面には大量のプラーク(細菌)が付着しています。この細菌が出す毒素によって、歯ぐきは慢性的な炎症を起こし、赤く腫れて、非常に脆い状態になっています。
- 血管の拡張と脆化:炎症が起きている歯ぐき内部では、免疫細胞を集めるために毛細血管が拡張し、血管の壁が薄く脆くなっています。
- 歯石除去時の刺激:スケーラー(歯石除去の器具)で歯石を剥がす際、この脆くなった歯ぐきにわずかな刺激が加わるだけで、簡単に血管が破れて出血します。出血が多いほど、歯ぐきの炎症が強い、つまり歯周病が進行している可能性が高いと判断できます。
出血は治療が進んでいる証拠
出血は一見すると怖いものですが、歯周病治療の観点から見ると、歯石という病原巣が除去された証拠でもあります。歯石が取り除かれることで、歯ぐきを刺激していた細菌の温床がなくなり、歯ぐきは徐々に炎症が治まって健康な状態へと回復し始めます。健康な歯ぐきは引き締まってピンク色をしており、歯石取りの際もほとんど出血することはありません。
したがって、歯石取りで出血した場合は、出血に驚くのではなく、「今、自分の歯ぐきは炎症を起こしている状態だ」と認識し、今後のセルフケアや定期的なメンテナンスの重要性を再認識する機会として捉えてください。
出血はいつまで続く?
歯石取りの際に出血した場合、多くの方が「この出血はいつまで続くのだろうか」と心配されます。結論から申し上げますと、処置後数時間から長くても当日中には止まるのが一般的です。しかし、歯ぐきの炎症状態によっては、翌日もごくわずかなにじむような出血が続くことがあります。
出血が治まるまでのプロセス
- 処置直後(数時間以内):歯石が除去された直後は、歯ぐきに残った微細な傷から出血が続きますが、これは通常、唾液に混じる程度で、時間とともに自然に凝固して止まります。歯科医院での処置後には、止血を促すためにガーゼを噛んでいただくこともあります。
- 処置の翌日まで:特に歯周病が進行しており、歯ぐきの炎症が非常に強かった部位や、深い歯周ポケット内の歯石を除去した場合は、翌朝の歯磨き時などに、ごく微量のにじむような出血が見られることがあります。これも通常は心配する必要はありません。
- 重要な回復期間(数日~1週間):大切なのは、この出血が落ち着いた後の数日間です。歯石が除去されたことで、歯ぐきは炎症が治まる方向へと回復期に入ります。出血が止まったからといって歯磨きを怠ると、すぐにプラークが溜まり、炎症が再燃してしまいます。
出血を早く抑え、回復を促すために
回復を早め、出血の再発を防ぐためには、以下の点に注意することが重要です。
- 優しく丁寧な歯磨き:出血が怖くて歯磨きを控えるのは逆効果です。出血部位も優しく丁寧に磨き、プラークを残さないようにしてください。ただし、硬すぎる歯ブラシの使用や、ゴシゴシと力を入れすぎる磨き方は避けてください。
- 刺激物の回避:処置当日は、熱すぎるものや刺激の強い食べ物・飲み物は控えめにし、アルコールの摂取や激しい運動は避けることで、血流が過度に良くなるのを防ぎ、止血を促します。
- うがいのしすぎに注意:頻繁に強くうがいをすると、せっかく固まり始めた血の塊(かさぶたのようなもの)が剥がれてしまい、再出血の原因となるため、控えめにしてください。
もし、出血が丸一日以上経っても止まらない、あるいは多量に続いたり、ズキズキとした強い痛みが伴う場合は、お口の状態を再確認する必要がありますので、ご連絡ください。
痛みを感じたり、出血は意外と多く症状として出ます。
歯石取りの処置中に痛みを感じたり、大量の出血を経験したりすることは、患者様にとって不安な体験かもしれません。しかし、これまで解説した通り、これらの症状はお口の健康状態によっては、意外と多く見られる自然な反応であり、特に歯周病が進行している方にとっては、治療のプロセスで避けて通れない初期症状であることがほとんどです。
症状が出やすいのは「歯周病のサイン」
痛みや出血といった症状は、ご自身の歯ぐきが「健康ではない状態」であることを教えてくれている重要なサインです。
|
症状 |
意味合い |
|
痛み・刺激 |
歯ぐきが炎症で敏感になっている、あるいは歯の根元が露出し知覚過敏を起こしている。 |
|
出血 |
歯石による細菌の刺激で歯ぐきが腫れ、毛細血管が脆くなっている。 |
これらの症状が出ることで、「もっと積極的に歯周病ケアに取り組む必要がある」という警鐘を鳴らしてくれています。逆に、歯周病が無く健康な歯ぐきであれば、歯石取りをしてもほとんど痛みや出血は起こりません。
大切なのはその後のケア
歯石取りの処置自体は、あくまで歯周病治療のスタートラインです。痛みや出血が落ち着いた後、歯ぐきが本来の健康な状態に回復するためには、患者様ご自身による日々の丁寧な歯磨き(セルフケア)と、歯科医院での継続的なチェック(プロフェッショナルケア)が不可欠です。
痛みや出血を経験したことで、歯石取りを敬遠してしまうのは、歯周病を進行させることにつながりかねません。大切なのは、これらの症状を治療の一環として受け止め、症状を繰り返さないために、歯科医院と協力して予防に取り組む姿勢です。私たちは、患者様一人ひとりに合わせた、痛みに配慮した処置と、その後のケアのアドバイスを丁寧に行うことで、皆様の口元の健康を長期にわたってサポートしてまいります。
監修

院長 宍戸 孝太郎
資格・所属学会
- 厚生労働省認定歯科医師臨床研修医指導医
- SBC(Surgical Basic Course 歯周形成外科コース)インストラクター
- SAC講師
- club SBC
- 日本口腔インプラント学会認定医
- 日本口腔外科学会会員